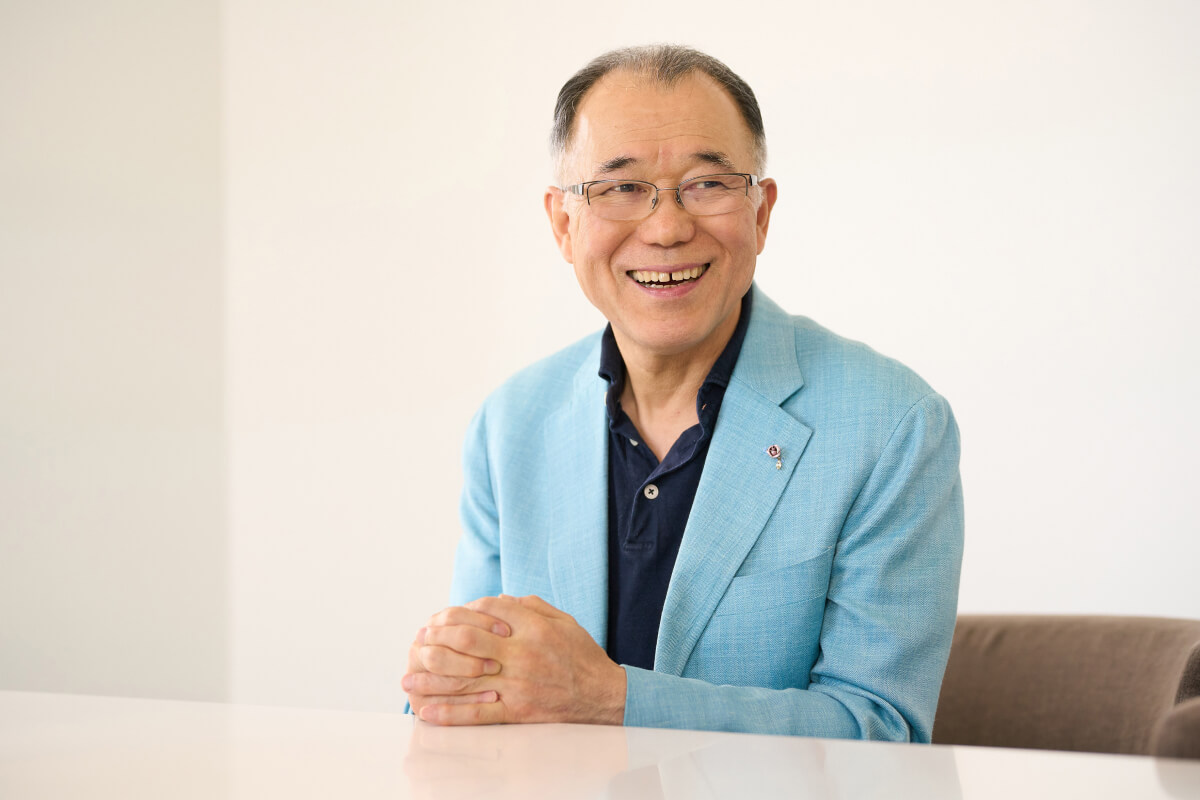Interview 01
共修社で磨いた「人とのつきあい方」が、
社会人としての土台になった
Profile プロフィール
学校法人角川ドワンゴ学園 理事長
山中伸一さん
1954年、都留市生まれ。県立都留高校卒業後、東京大学法学部入学と同時に1972年に山梨共修社入寮。1977年、文部省(現・文部科学省)に入省し、文部科学審議官、文部科学事務次官などを歴任。退官後は駐ブルガリア特命全権大使を務め、2018年から現職。

帰れば誰かいる居心地のいい、安心できる寮
修社のことは、地元の都留市に社友(OB)がいた関係で、親から聞いて知りました。当時は1万円くらいかな、寮費が安くて交通の便も良い立地ですし、入寮試験を受けることにしました。
入寮後に感じたのは、山梨県人ばかりが集まっている安心感と居心地の良さ。国中とは少し言葉が違う郡内の出身なので、「ささらほうさら」とか、共修社に来て初めて聞いた甲州弁もありました(笑)。寮に帰れば必ず誰かがいて、娯楽に興じたり、話に花を咲かせたり、一緒に野球中継を観たり、麻雀をしたり、上京して寂しさや孤独を感じたことがなかったですね。後輩が「毎日キャンプに来ているようです!」と言っていたのも覚えています。
年1回の社友会(寮祭)や上野公園でのお花見など、イベントもたくさんありました。とくに印象深いのは社交ダンス。先輩から踊り方を教わって、近所にある大学の女子寮に声をかけて、そこの学生を共修社に招いてダンス会をやるんです。みんなとソワソワしながら、女子学生とのダンスを楽しんだのは良き思い出です。

40人との共同生活の中で、
自然に身についた社会性
そんなふうに共修社で生活していくことで、自然と社会性が身につきました。40人以上が住んでいますから、なにか問題が出てくるたび、なんとか解決していかなくてはいけません。高校までの狭い人間関係とは違う、個性的な寮生たちとのつきあいの中で「いろんな人がいるんだ」と気づきますし、そこで揉まれていくうちに「こなれた」コミュニケーションができるようになるんです。社会人になったとき、この力が役に立ちました。仕事をするうえでの前提となる、人とのつきあい方、話し方、そして話の聞き方は、共修社で磨かれたと思います。
卒業から半世紀近く経った今でも、同期や近い年次の先輩・後輩と、毎年お正月に集まるのが恒例になっています。郡内地区出身者の会もあったりして、「無尽」のような感じでつきあいが続いています。
同郷の仲間が集まる共修社で、
「自分で考える力」を養ってほしい
現代社会には、かつて存在したような「安全・安心なルート」はなくなり、正解のない、絶えず変化する時代になっています。その中で、共修社に集う学生のみなさんに身につけてもらいたいのは、「自分で考える力」です。情報があふれ、そのスピードも速い今だからこそ、「みんながやっているから」と周りに流されるのではなく、自分で考えて判断して、行動する経験を重ねてください。
そのときに、一人で考えるだけではなく、周りにいる仲間に相談できるのが、共修社の強みです。しかも、同じ山梨出身の人たちが集まっているので、心も通じやすい。その環境を最大限に生かしながら、充実した学生生活を送ってほしいですね。